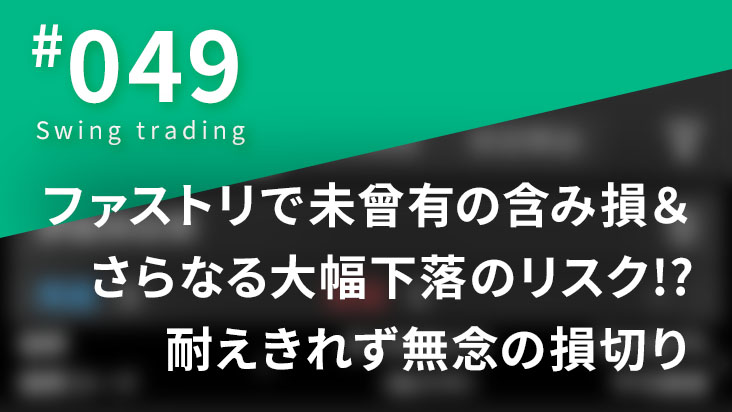2025年1月10日から15日にかけておこなったスイングトレードの結果についてレポートします。
ファーストリテイリング(9983)
-315,698円の特大損切り
300株を買建し、+36,466円の利確、-315,698円の損切りという大惨敗に終わりました。
僕にもっと恐怖に耐える図太さあるいは潤沢な資金があれば利確できていたであろう300株でしたが、30万円オーバーの含み損に加えてさらなる下落の可能性に対する恐怖が重くのしかかり、「一旦損切りして買い直し」という判断をするに至りました。
しかしこれがなんとタイミングの悪いこと。
損切りした数分後には株価が上昇を始め、その翌日には利確ラインまで到達しました。
まったくもってやるせない。
「やってられない」この一言に尽きる、後味の悪いスイングトレードとなりました。
| 期間 | 株数 | 買建時単価 | 売埋時単価 | 損益 | 金利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10〜1/14 | 100株 | 48,200円 | 48,570.20円 | +36,466円 | 554円 |
| 1/10〜1/15 | 100株 | 49,300円 | 47,650.00円 | -165,850円 | 850円 |
| 1/10〜1/15 | 100株 | 49,140円 | 47,650.00円 | -149,848円 | 848円 |

48,200円の建玉を先に利確
48,200円の建玉を先に利確したのは、その後もしまた48,200円未満に下がられたとき、含み損のインパクトを100株分でも減らしておきたかったからです。
「上がるだろう」とは思いつつ、「まだ下がる可能性も十分にある」と考えていたのです。
ファーストリテイリング(9983)という銘柄は放っておけば上がる銘柄だと思っています。
が、一時的にせよ数十万円の含み損を抱えたまま日々過ごしていくのはやはり辛いものがあります。
実際、建玉が300株から200株になっただけでも、その瞬間に心が軽くなったのを感じました。
株価はさらに下落 含み損は一時-372,000円に
1月14日の安値は47,360円。
この時、含み損は200株で-372,000円にもなっていました。
が、まだ耐えられる。
「上がる」と信じているからこそ、これほどの含み損もそれだけならまだ耐えられる金額でした。
「キャップ調整懸念でさらなる下落の可能性」さえなければ。
キャップ調整懸念でさらなる大量売り→大幅下落の可能性
日経平均株価に対してファーストリテイリング(9983)の株価が占める割合(ウェート)が、この時点でも11%を超えており、依然としてキャップ調整が実施される懸念は拭い去れません。
このままのウェートで1月を終えることになれば、日経平均連動型のファンドから大量の売りが出てくることが予想されており、そうなればさらなる大幅下落は避けられません。
そうなった場合、含み損は果たしていくらになるのか。
「もしや100万円規模まで膨れ上がるのでは?」といった不安も膨らみ始めます。
「どうせ上がる」とは思っているものの、利確できるとしても数万円です。
そのために一時的とはいえ100万円規模(根拠のない想像値ですが)のリスクを負うのは割りに合いません。
信用買いの買い方金利も心配
株価が上がるとすれば、1月末日のウェート判定期日を過ぎ、おそらくキャップ調整がおこなわれることが決定し、日経平均連動型のファンドから大量の売りが出て、ひとしきり落ち着いてからということになります。
とすれば、株価が上がり始めるのは早くとも2月の中旬から後半。
もしかしたらもっと遅くなる可能性すらあります。
その期間、49,000円規模の銘柄300株を信用で持ち続ければ、金利もバカになりません。
例えば49,300円の株を100株30日間持ち続ければ、金利は11,345円にも上ります。
つまり、ファーストリテイリング(9983)の株を300株信用で1か月間持ち続ければ、それだけで30,000円以上のコストがかかってしまうことになります。
これではせっかく利確できたとしても赤字になってしまう可能性すらあります。
そこで、一旦ここで損切りしておいて、どうせしばらくはこのままの株価でヨコヨコするだろうから、そろそろ上がるかな、というタイミングで買い直せば良い、と考えました。
売れば上がる
- 一時的とはいえ莫大な金額の含み損を抱えることに不安を感じた
- 信用買建の長期間保有による金利コストを重く見た
上記2点の理由により一旦損切りをしたわけですが、その直後、一気に買いが入り株価は急上昇。
48,000円を超えていきます。
そしてこの日(1月15日)の終値は48,340円。
高値引けです。
翌日1月16日。
寄前の気配は買い優勢。
気配値は一時49,000円を示していました。
寄り付けば始値は48,800円。
300株合計での利確ラインにあと80円と迫る株価です。
「おいおいマジか…」と言いたくもなります。
株価はゆっくりと下落するものの、またすぐに上昇に転じ、9時30分には49,010円に到達。
9時34分には高値49,020円を記録しました。
もしここまで300株をホールドできていれば、ひとまずほぼ同値撤退まではできていたはずでした。
2024年10月にもキャップ調整はあった
日経平均算出の定期見直し基準日は1月末日と7月末日となっています。
2024年7月31日大引時点で、ファーストリテイリング(9983)のウェートはキャップ水準の10%を超え、同年10月1日にキャップ調整比率0.9が設定されました。
「ファーストリテイリング」に対する指数算出上の取り扱いについて
日経平均株価、ファーストリテイリングの構成比率引き下げ 基準「10%」超え – 日本経済新聞
ファストリ株、初の日経ウエート上限超過 リバランス売り圧力にも | ロイター
この時の株価は日足で見ると下図のようになっています。

7月11日を頂点に、月末に向けてズルズルと下落しているのがわかります。
おそらくウェートを下げようとする意図、あるいは、大量の売りによる株価下落に対するリスクオフで各方面から売りが出てきたものと思われます。
この前の基準日である2024年1月31日に際しては、同社代表取締役会長兼社長の柳井正氏が断続的に株式を売却していたことが2月9日提出の報告書で判明しており、7月の基準日に向けてもおそらく同様の動きがあったでしょう。
ファストリ株、柳井会長がウエート基準日前後に一部売却 次回7月に思惑も | ロイター
ファーストリテイリング柳井正氏が同社株売却 保有比率1%減 – 日本経済新聞
2024年8月5日は記憶に新しい日本株大暴落が起きており、キャップ調整の影響がどのように出ていたのかがわからなくなっています。
大暴落から8月いっぱい一気に駆け上がった株価が9月に入って急落しており、これがキャップ調整を意識してのまとまった売りと見られています。
が、ひとしきり下げた後はまた一気に上昇しており、これでキャップ調整の影響によるリバランスの売りは出切ったものと思われます。
ファーストリテ—大幅続落、キャップ調整による売り需要の発生をあらためて意識 投稿日時: 2024/09/05 10:42[フィスコ] – みんかぶ
10月2日にも大きめの陰線を作っていますが、その後は禊を終えたかのように上昇。
10月15日には始値で55,300円に到達(終値は53,520円)しています。
大幅下落時の下げ幅は直近高値から-5,000円程度が目安?
2024年7月にキャップ調整を意識して売られた際も、8月5日の大暴落の際も、9月にキャップ調整を意識して売られた際も、おおよそ直近の高値から-5,000円程度の下落にとどまっています。
10月15日に場中で55,000円を突破した後の下落も10月31日にかけて50,000円付近まで下落しており、下げ幅はやはり-5,000円ほどです。
1月17日時点で、ファーストリテイリング(9983)の株価終値は48,060円となっています。
直近高値2024年12月27日の終値54,690円から差し引くと-6,630円安となります。
株価は1月14日以降概ねこの48,000円ラインを保持しようとしており、どうやらこの辺りが今回の下げ幅いっぱいか?と思えなくもないところですが、果たして…。
とにかく「悔しい」の一言に尽きる結果
今回のスイングトレードを一言で表すのであれば、とにかく「悔しい」の一言に尽きます。
1月14日の37,600円付近の推移が1月いっぱいは続くだろうと予想して一旦損切りしたのですが、この予想が完全に外れて株価はすぐに上昇。
「なんのための損切りだったのか」と心の底から悔しさが込み上げます。
ただ、唯一の救いは株価がそのまま一気に上昇していかなかったことです。
値動きはその後また下落基調となり、1月17日時点の終値では48,060円となっています。
想定より若干上がってはしまったものの、まだ上昇の余地は十分に残っています。
タイミングを見計らってこのあたりの株価で買建することができれば、勝機は十分にあります。
とはいえ、その「タイミングを見計らう」のが極めて難しいわけですが…。
「損失を取り返そう」とすればまた痛い目を見ることになるでしょう。
「チャンスがあれば、なるべくならモノにしたい」くらいの気持ちでウォッチを続けたいと思います。
【1月21日追記】終値で49,000円に到達
1月末日に日経平均採用銘柄の見直し基準日があり、ここに向けてウェートを10%未満に持っていきたいところだったでしょうが、1月21日大引時点でウェートは11.15%となっています。
さすがに無理筋と諦めたのか、あるいは何かしら別の思惑か、徐々に株価が上昇の兆しを見せています。
例えば指数連動系ファンドから大量の売りが出てきて株価が急落するとしても、それまでに株価が55,000円まで回復していれば、ドカッと下がっても50,000円付近が底値になるかもしれません。
とすれば、今買っておけば十分に利益が出る計算。
もしかしたらそういったような思惑もあるかもしれません。
実際、僕自身も現物資金に余裕があれば48,000円を割ってきた段階で買ってしまいたかったところです。
が、残念ながら現物資金はなく、信用で買建してしまえば株価が上昇するまでの長期間金利が発生してしまうため諦めたという経緯があります。
買うとしてもすでに出遅れ感のあるタイミング。
また、買ったら買ったでまた下がられてはかないません。
なかなか難しい局面になってきました。
株価は果たしてこのまま上昇していくのか、あるいはどこかのタイミングでまた調整が入るのか、要注目です。