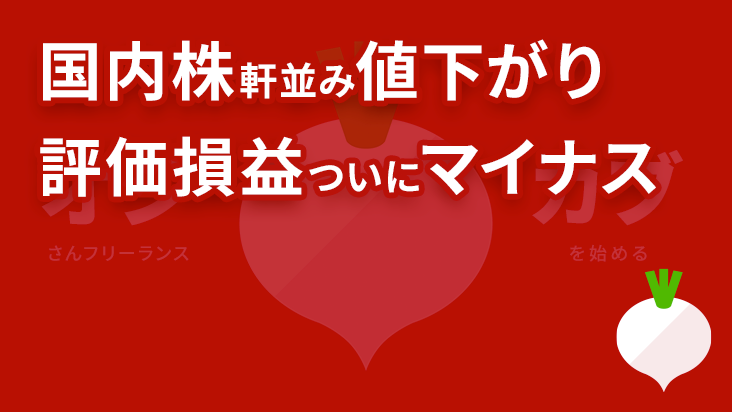4月10日にはアメリカのCPI(消費者物価指数)が、11日には同PPI(生産者物価指数)が発表され、その結果を受けてアメリカ株式市場でリスクオフの動きが活発化。
その影響が日本の株式市場にも現れ始め、日経平均の下落が始まりました。
また、イランとイスラエルの緊迫した情勢もあり、株価の下落に一層の拍車がかかります。
4月19日には、「イスラエルがイランに対して反撃」といった誤った情報が流され、一時は日経平均株価が前営業日比-1346.64円の36,733.06円をマークするなど、日本の株式市場に大きな混乱が引き起こされました。
19日午前中に大崩れした日経平均株価も、午後には若干持ち直しましたが、それでも前営業日比1,011.35円安の37,068.35円で大引を迎えています。

保有銘柄・建玉の含み益が減少、含み損が増大
これを受けて、僕が保有している銘柄や建玉の含み益が減少、または含み損が増大しています。
含み益が出ていた銘柄のほとんどが含み損に変わってしまいました。
僕が保有している銘柄において、現時点での国内株式の評価損益は-266,358円、米国株式の評価損益は-16,437円となっています。
投資信託がかろうじて+49,488円となっていますが、こちらも来週以降どうなるか。
また、スイングトレード対象として買建している建玉の評価損益も-615,237円と、なかなかにシビれる金額となっています。
こちらは前述したような世界情勢を受けての下落というよりは、どちらかというと仕手による株価操作のような部分が大きいかと思っていますが。
このスイングトレードの目論見としては、来週後半にはある程度株価が回復し、そこで利確と考えています。
が、さて、こちらも果たしてどうなるか。
今後の見通しはあまり明るくなさそう
今回の株価の下落については、要因が3つあると考えられています。
- アメリカの半導体市場の低迷
- アメリカの金利引き下げ回数が予定より減少する(あるいは実施されない)可能性
- 中東情勢
これらを鑑みると、日本単体ではもちろんどうしようもなく、かといって外交でどうにかできるものかと言えばそれもおそらく不可能かと思われます。
現状日本の株式市場は、アメリカの思惑次第、中東情勢次第と言ってもいいのではないでしょうか。
アメリカの半導体市場
アメリカの半導体市場については、市場そのものが果てしなく沈んでいくということは考えづらく、どの程度の期間でどの程度回復するか、ということになるのかと思います。
ただ、ここ最近の過度な加熱感が今回一旦リセットされ、地に足の着いた動向になっていくのではと思います。
アメリカの金利引き下げ
金利引き下げについては、なかなか難しいという見方が有力のようです。
アメリカ市場では、生産者側も好調、消費者側も好調ということで、利下げの必要性が薄れているようです。
中東情勢
こちらはどうなるのかまったく不透明です。
先週金曜日の段階では予断を許さない状況で、それゆえに不穏な情報が錯綜するなどして株式市場にも混乱を招きました。
ただ、最新の情報では「イラン、イスラエル双方とも幕引きを図りたい考えで静観」といったニュアンスのものがありました。
これが本当なら、こちらは来週以降どうにか落ち着いていくのかもしれません。
が、こればかりはあまり楽観的に構えるわけにいきません。
本格衝突避け幕引き図る 攻撃受けたイラン、静観の構え―レーダー標的にとどめたイスラエル:時事ドットコム
日経平均 反発か さらに下落か
「そろそろ押し目狙いの買いが入り反発する」という見方をする向きもありますが、さすがにこれによって40,000円付近まで戻すという可能性は低いように思われます。
しかも、前述したようなアメリカの状況や中東情勢を鑑みると、その後その水準をキープし続けていけるのかも微妙な気がします。
そうなると、下落はさらに続き、目安としては36,000円付近、または33,000円〜34,000円付近まで下落するのではという見方もされています。
2月初旬、1月初旬にそれぞれ発生している、急加速した株価の上昇をリセットするような下落、ということでしょうか。
日経平均株価は、2023年6月あたりから同年末までの半年ほど、32,000円〜33,000円付近で横ばいに遷移していた時期があります。
2024年1月からの上昇はおそらく新NISA効果ではないかと思うのですが、今回の株価急落を受けて、1月から投資を始めた個人投資家たちが一斉に狼狽売りを始めると、株価の下落はかなり大きいところまで進みそうな気がします。
もちろん、株式市場の盛り上がりに合わせて機関投資家や大口投資家も買いを進めているでしょうから、2023年末の水準まで下げるということはないのだろうと思いますが、果たしてどこまで下げるのか…。

売るも自由 売らぬも自由
例えば日経平均を月足で5年分見てみると、下記のように上昇しています。

さらに、10年で見てみると下記のような上昇になります。

つまり、直近下落(暴落)や横ばいがあったとしても、長期で見れば株価は上がる可能性のほうが高いと考えます。
もちろんこれは「日経平均」の話であって、個別銘柄それぞれの株価となればまた印象も変わってはきますが。
ちなみに投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の5年間のパフォーマンスを示すグラフは下記のようになっています。
こちらもやはり、時折下落や横ばいを示しながらも上昇している様子が見て取れます。

ただ、何かしらの理由があって損失が出ているタイミングで投資をやめなければならなくなった場合などは、結果的には資産の減少ということになってしまいます。
こればかりは致し方なしと言う他ありません。
こういったリスクがあることは、株式投資や投資信託を開始する時点で織り込み済み。
それでも続けるのか、キッパリと別の資産形成に舵を切るのかは、各々が判断するべきことですね。
個人的には、まだ株式投資をやめるつもりはありません。